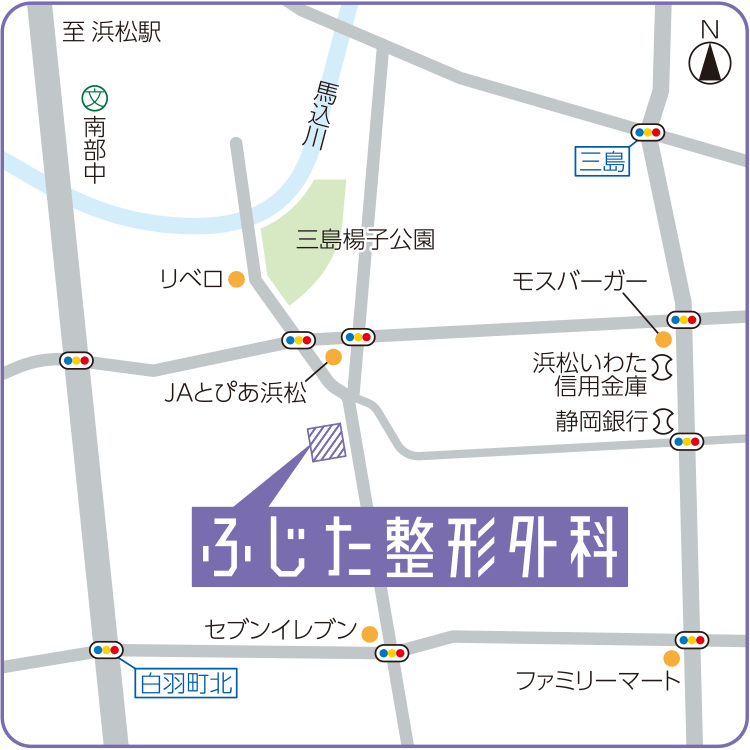骨粗しょう症とは

骨粗しょう症とは、骨の密度や質が低下して骨がもろくなり、骨折しやすくなる疾患です。
年齢を重ねた方、とくに女性に多く見られる病気で、自覚症状が乏しいまま進行するため、「サイレントディジーズ(静かな病気)」とも呼ばれています。
気づかないうちに骨の強度が落ち、ちょっとした転倒や動作で骨折してしまうリスクが高まります。
近年では男性でも骨粗しょう症が増加傾向にあると言われていますが、これは糖尿病や慢性腎臓病などの生活習慣病が原因となって骨粗しょう症が引き起こされているためと考えられています。
骨粗しょう症が起こるしくみ
私たちの骨は、古くなった骨を壊して新しい骨をつくる「骨代謝」の働きによって、常に新陳代謝が行われています。
しかし、年齢やホルモンバランスの変化などにより、このバランスが崩れ、骨を壊す働きが骨をつくる働きを上回ると、骨量が減少していきます。
これが骨粗しょう症の主なメカニズムです。
骨粗しょう症が起こる原因
骨粗しょう症の原因には、加齢や閉経による女性ホルモン(エストロゲン)の減少、カルシウムやビタミンDの不足、運動不足、喫煙、過度の飲酒、ステロイド薬の長期使用、さらに糖尿病や甲状腺機能異常などの疾患が挙げられます。
とくに閉経後の女性や高齢者では、原因が重なり合って進行しやすくなります。
骨粗しょう症の症状
骨粗しょう症は初期には自覚症状がほとんどありませんが、以下のような症状がみられる場合は注意が必要です。
- 背中や腰の痛みが続いている
- 昔より身長が縮んだと感じる
- 背中が丸くなってきた
- 転びやすくなった、ふらつきやすくなった
- とくに強い衝撃もないのに骨折を経験した
このような症状がある場合、すでに骨がもろくなっている可能性があります。
早めの検査が推奨されます。
骨粗しょう症は放っておくと、骨折のリスクが高まり、「脆弱骨折」を引き起こして生活の質(QOL)に大きな影響を与えます。
とくに背骨(脊椎)、股関節、大腿骨などの骨折は、寝たきりや要介護状態につながることもあります。
骨折後の生活動作の制限や長期入院が必要となり、患者様ご本人だけでなくご家族の生活にも影響が及ぶことがあります。
また1カ所骨折すると次々に骨折が連鎖してしまう「ドミノ骨折」を起こすこともありできるだけ早い段階での治療が必要です。
脆弱骨折とは
脆弱骨折とは、健康な人なら骨折しない程度の軽い衝撃で起こる骨折のことです。
たとえば「つまずいて尻もちをついただけで腰の骨(脊椎)を折った」「軽く手をついたら手首を骨折した」などが代表例です。
骨折部位によっては、寝たきりにつながりやすく、高齢者の生活自立度を大きく下げる原因になります。
こうした骨折を予防するためにも、骨粗しょう症の早期診断と治療が重要です。
骨粗しょう症によって引き起こされやすい脆弱骨折としては、以下のようなものがあります。
脊椎圧迫骨折
背骨(胸椎・腰椎)が押しつぶされるように骨折します。
転倒や重い物を持ち上げた際に起こりやすく、背中や腰の痛み、身長の低下、円背を招きます。
くしゃみをしただけでも気が付かないうちに骨折することがあり、「いつのまにか骨折」とも呼ばれます。
大腿骨近位部骨折
太ももの付け根(股関節周辺)に起こる骨折で、転倒時や足をひねった時などに多発します。
歩行困難や寝たきりの原因となり、高齢者の介護リスクが急激に高まります。
上腕骨近位端骨折
肩に近い上腕骨の上部が骨折します。
転倒して手をついた際や肩を強打したときに発生し、腕の動きが制限され、着替えや洗髪が困難になります。
橈骨遠位端骨折
手首の骨(親指側にある橈骨の先端)が骨折します。
転倒して手をついたときに起こりやすく、手首の腫れや痛み、物を握る・持つ動作が困難になります。
骨粗しょう症の検査
骨粗しょう症は自覚症状がほとんどないため、ある程度の年齢になったら、一度、検査を受けてみることをおすすめします。
とくに50歳以上の女性はリスクが高いため、要注意です。
検査法としては、以下のようなものがあります。
骨密度測定
X線や超音波を使って骨密度を測定し、年齢や性別ごとの基準と比較します。
骨密度の測定法の種類は、次の通りです。
- DXA(デキサ)法
- 2つの異なるエネルギーのX線を利用して行います。主に大腿骨近位部や腰椎の骨密度を正確に測定するものですが、全身に用いる場合もあります。
- 超音波法
- X線を用いないため、妊娠中の方でも測定することが可能な検査です。かかとや脛の骨に超音波を当てて簡易的に測定します。
- MD(エムディ)法
- 手の骨と厚さの異なるアルミニウム板とを同時にX線撮影し、骨とアルミニウムの濃度の比較によって測定します。
当院ではDXA法にて腰椎、大腿骨の測定を行い、できるだけ正確な骨密度の評価を行っています。
X線検査
すでに圧迫骨折などの骨折をしていないか、骨の変形がないかを確認します。
血液検査・尿検査
カルシウム、ビタミンD、骨代謝マーカーなどを測定し、骨の新陳代謝の状態を評価します。
診断基準としては、DXA法による数値が、若年成人平均値(YAM)に対して、何%に相当するかによって骨密度の診断を行います。
YAMの80%以上なら正常、70%以上80%未満なら骨量減少、70%以下であれば骨粗しょう症と診断されます。
骨粗しょう症の診断
検査の結果で以下の場合骨粗しょう症の診断になります。
- 脆弱骨折のうち「脊椎圧迫骨折」「大腿骨近位部骨折」がある場合(骨密度によらず)
- 「脊椎圧迫骨折」「大腿骨近位部骨折」以外の脆弱性骨折があり、YAM値が80%未満である場合
- 骨折がなくてもYAM値が70%以下の場合
骨粗しょう症の治療
骨粗しょう症の治療は、病状の進行を防ぎ、骨折リスクを低下させることを目的に行われます。
大切なのは、食事や運動などの生活習慣を見直していくことと、適切な薬による治療を組み合わせていくことです。
生活習慣の見直し
日々の生活を見直すことも大事です。 患者様とともに、以下のような対策に取り組んでいきます。
- 骨のもととなるカルシウム(牛乳・小魚など)や、カルシウムの吸収を助けるビタミンD(魚・きのこなど)の摂取を意識する
- 定期的な日光浴で、皮膚でのビタミンDの生成を促す
- 筋力トレーニングやウォーキングなどの適度な運動を行う(骨への適度な負荷は骨を作る細胞を活性化させます)
- 禁煙・節酒を心がける
- 転倒を防ぐ生活環境の整備を行う
薬物療法
生活習慣の改善のみでは骨粗しょう症を改善させることは困難なことが多いのが現状です。
必要に応じて、医師の判断で薬物療法を開始します。
主な薬のタイプには以下のものがあります。
患者様の年齢、性別、骨密度、骨折歴などに応じて、最も適した治療法を選択します。
骨吸収抑制薬
- ビスホスホネート製剤:骨を壊す細胞(破骨細胞)の働きを抑えます
- デノスマブ:破骨細胞の形成を抑える注射薬です
- SERM(選択的エストロゲン受容体モジュレーター):女性ホルモンに似た作用で骨を守ります
骨形成促進薬
- 副甲状腺ホルモン製剤:骨をつくる働きを促進する注射薬です
その他
- ビタミンD製剤:カルシウムの吸収を促進し、骨質を改善します
- ビタミンK製剤:骨のたんぱく質の働きを助け、骨質の改善に寄与します
- カルシウム製剤:骨の主要な成分となるものです